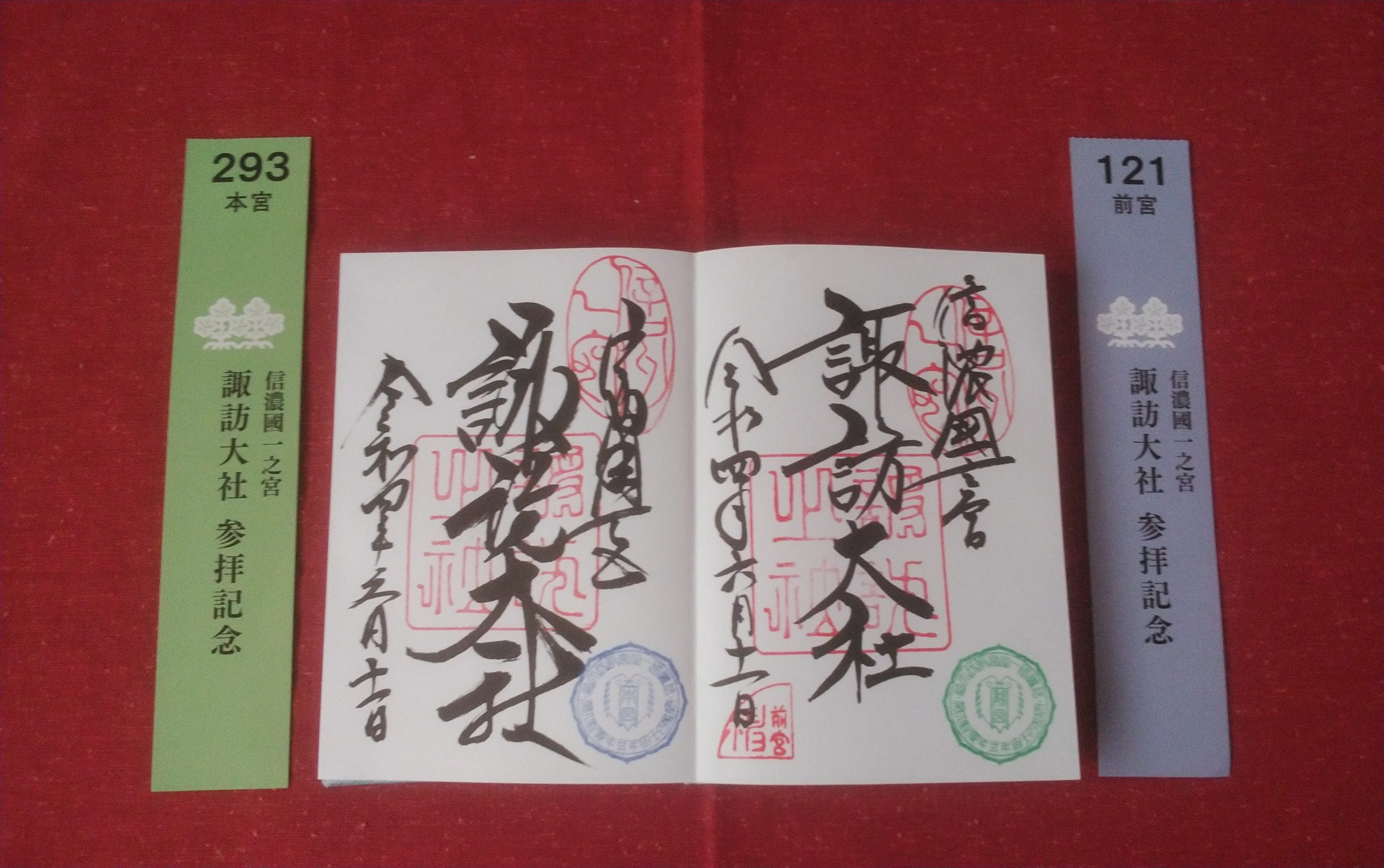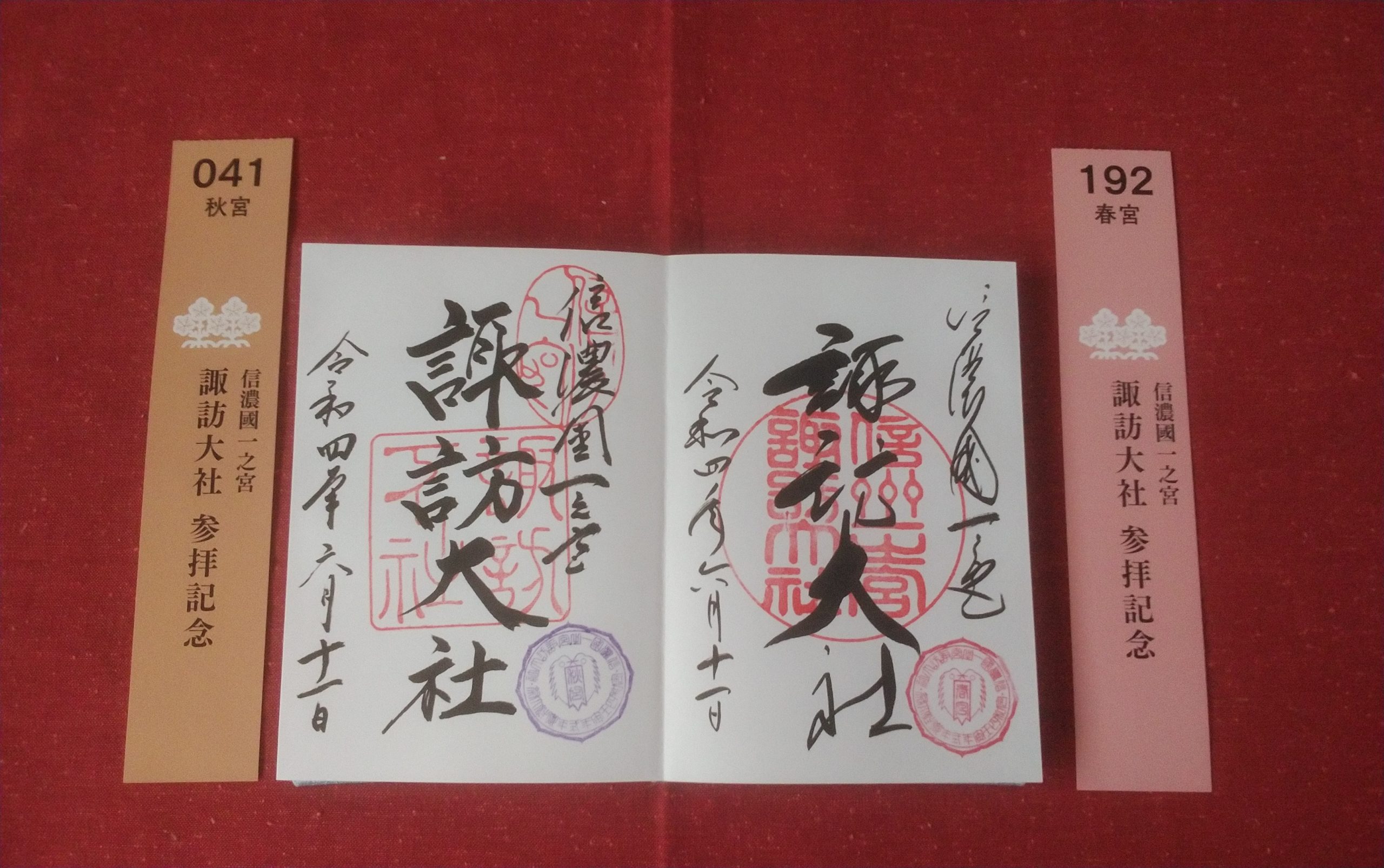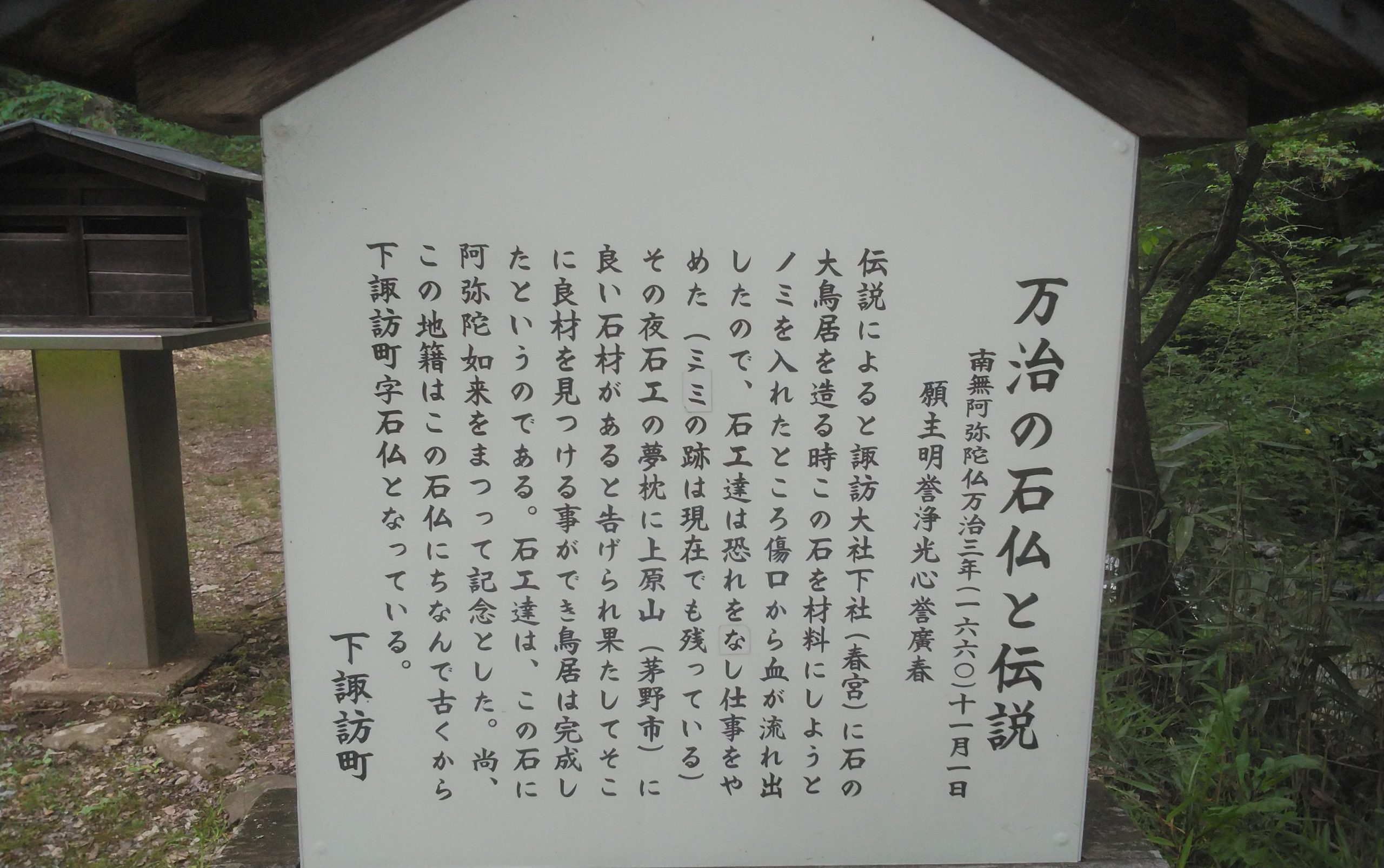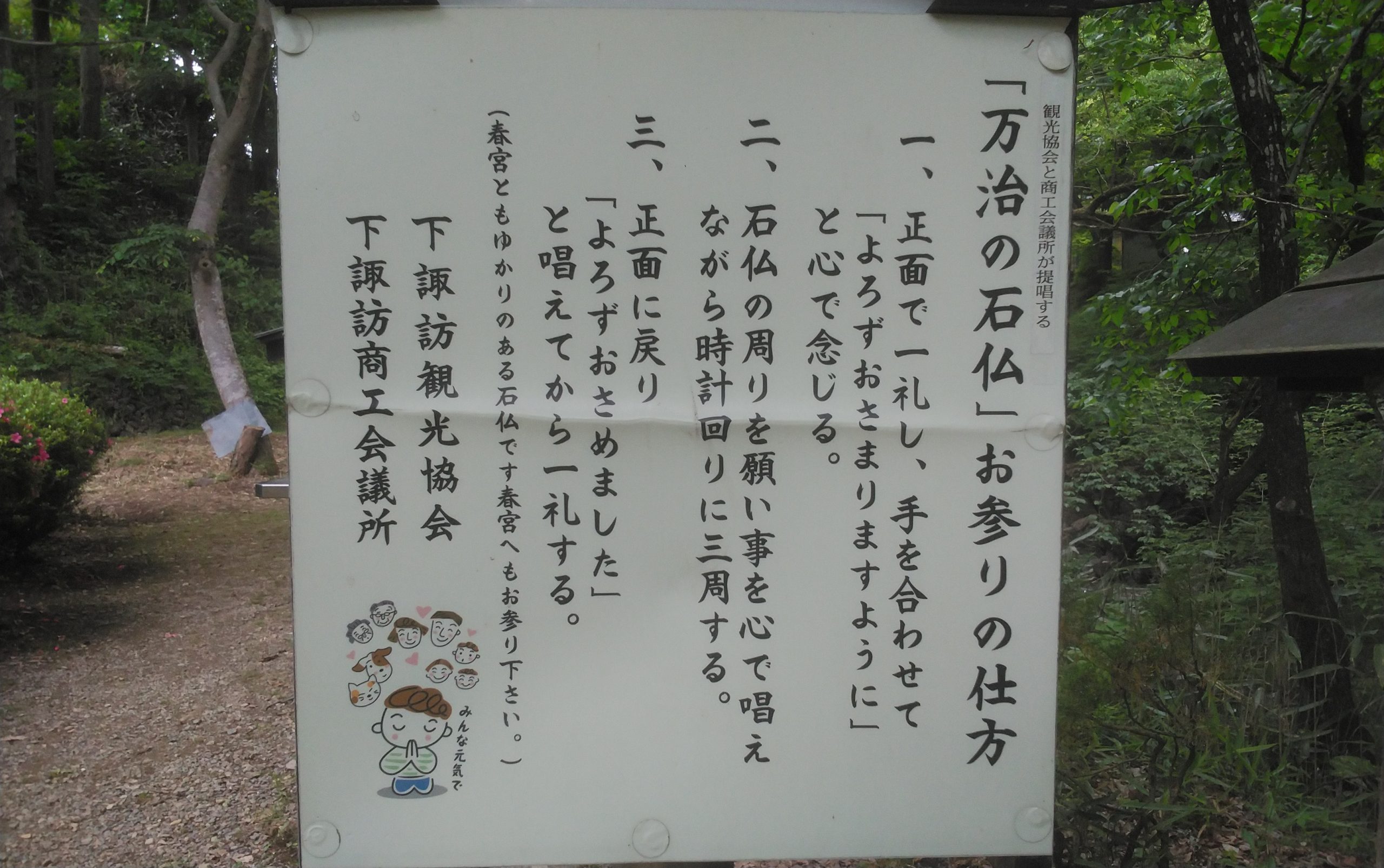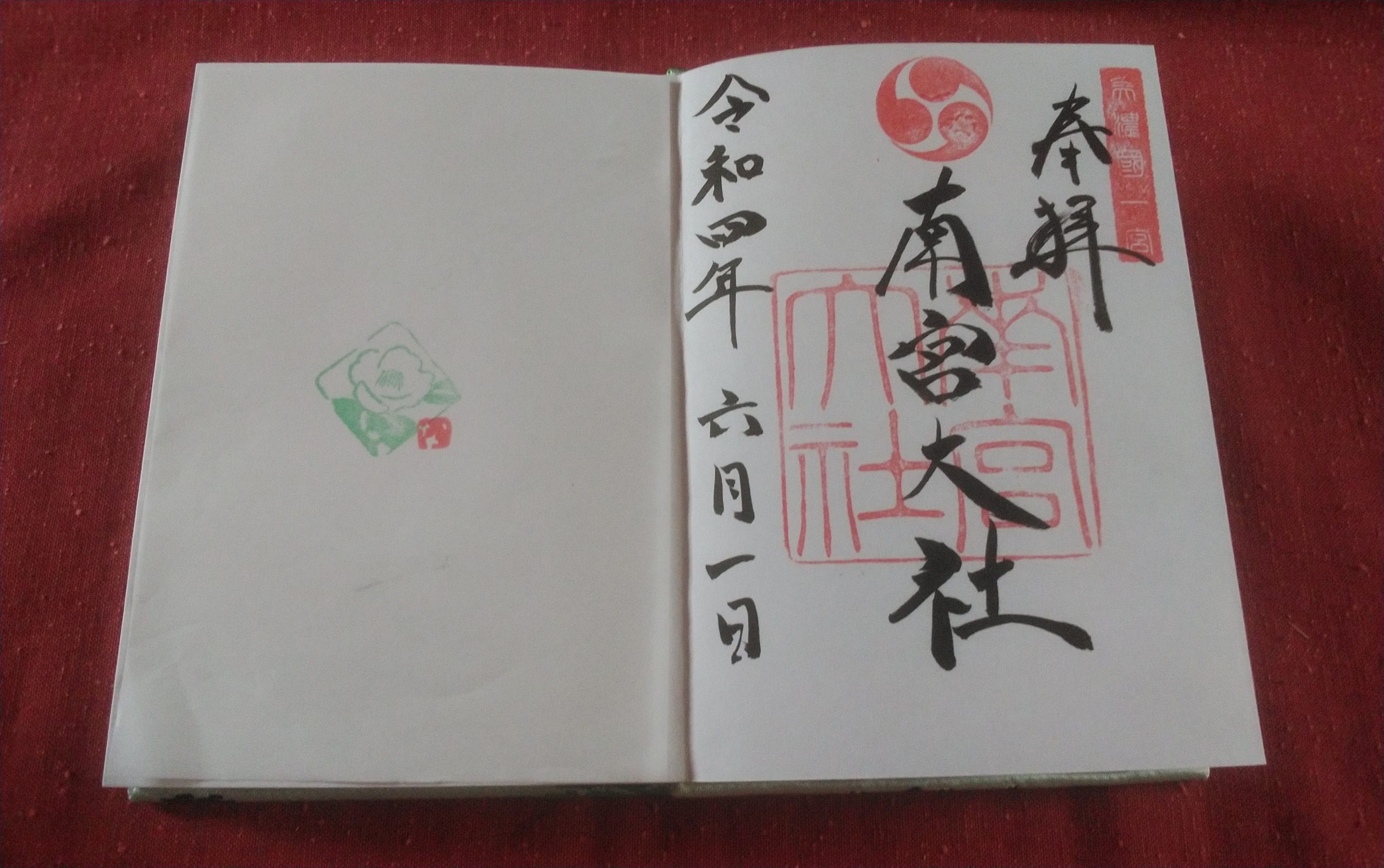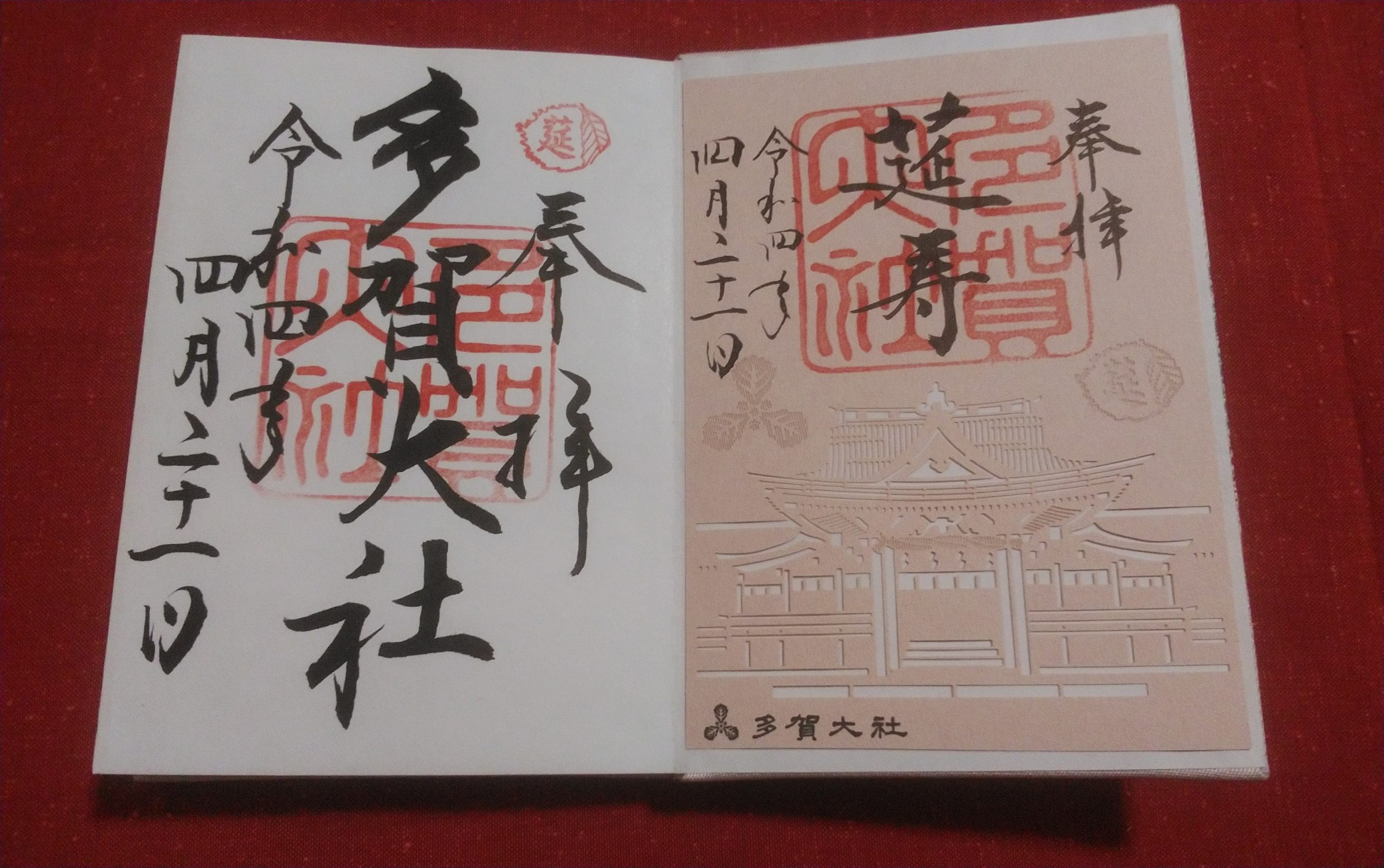《須弥山・しゅみせん》と、お題が付いた古谷石です!この石の特徴は、中央にある、そそり立つ【須弥山】にあります。
《須弥山・しゅみせん》と、お題が付いた古谷石です!この石の特徴は、中央にある、そそり立つ【須弥山】にあります。
須弥山とは古代インド仏教の世界観で、その仏教世界の中心にある想像上の山のことです。
更に頂上には三十三天に分かれ、その一つの喜見城に帝釈天が住み、他の三十二天を支配するというスケールである。
しかもその上に、五段界に分かれた世界があり、最上段の悲想非非想天(有頂天)というところが、如来の世界である。
これら須弥山が千集まって一小千世界といい、一小千世界が千集まって中千世界といい、大中小の区別がある故に、これを総称して三千大世界と称する。
そして全宇宙にはこのような大三千世界が限りなく存在するという。
その須弥山頂上の喜見城に如来さまがしばしば来臨し、人間の住む南贍部州(なんせんぶしゅう)に対して如来の法力を及ぼし、人間の前世・今世・来世の三世はもとより、我らの先祖代々一切にその功徳をもって供養をもって供養守護をして下さるとのこと。
そればかりか奈落の底まで如来の慈光は万遍なく届き四苦八苦の衆生を救済して下さるのである。
更にこの須弥山を守る四天王を始め、数えきれないほどの菩薩達が仏教信者を擁護して下さる。
しかも須弥山のまわりの東の方から、白銀の光・南からは瑠璃の光・西側からは頗梨(はり)の光・そして北の方から黄金の光が無限に広がる須弥山上空にその光を下から上に照らし、その四色の光が須弥山上空で混じり合い、言語に尽くせないおごそかな光となって、壮麗な仏国土を照らしている。
山の形は上と下の直径が大きく、腰が細く杵状の形で九山、八海、四州などから成立する。
須弥山の世界の根底は、風・水・金の三輪が成立する。
日本でも古くは、『日本書紀』に須弥山の記述があります。
また、飛鳥の石神遺跡から明治時代に出土した須弥山石も有名です。
日本庭園の須弥山形式では、中央に突出する岩を須弥山に例える石組です。
身近なお仏壇では、須弥壇を境に、上の部分が天上界、下の部分が地上の世界を表します。